知られざる水道の未来──「蛇口の向こう側で起きていること」
- 西園寺ケン
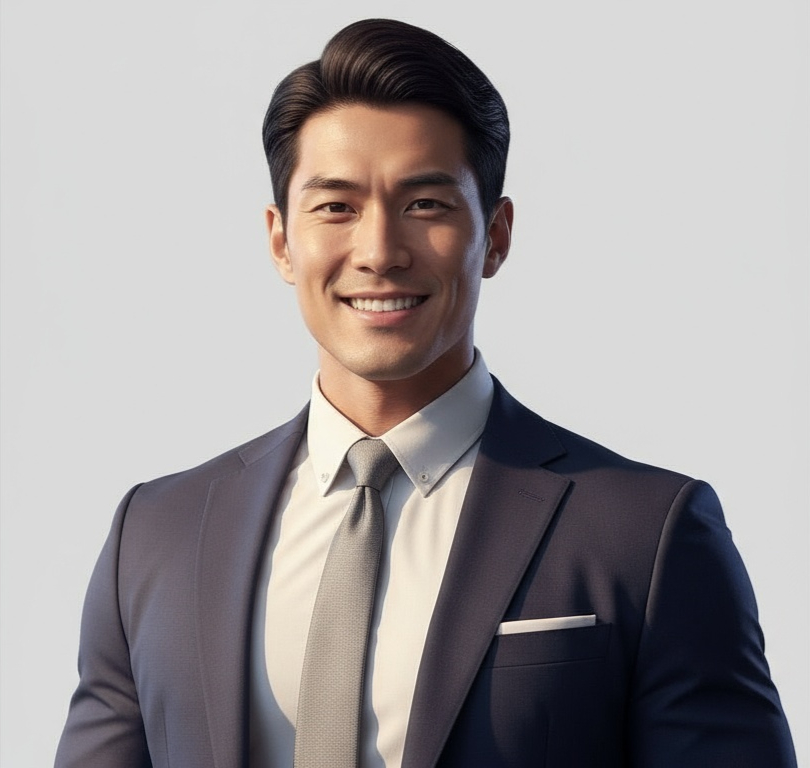
- 2025年11月10日
- 読了時間: 6分
目次
いつも通りの水道に潜む見えない危機
老朽化する水道管と、進む民営化の波
最悪の未来と、現実的な変化
自分たちの水を守るためにできること
いつも通りの水道に潜む見えない危機
朝、食器を洗いながらふと気づく――「あれ、なんだか水の匂いが気になる?」そんな経験はありませんか。普段、何気なく使っている水道水。けれど今、その“当たり前”が静かに揺らぎ始めています。
日本全国で、水道管の老朽化が深刻な課題となっています。高度経済成長期に整備された水道管の多くは、すでに寿命の40年を超えています。全国の上水道管のうち、2割以上が耐用年数を過ぎたまま使用されているというデータもあり、2030年代にはその割合が7割に達するとも言われています。
古くなった管は錆び、内側から剥がれた金属片や鉄分が水に混ざります。「赤水」と呼ばれる茶色く濁った水や、カルキ臭、独特のにおいを感じることも。見た目ではわからなくても、微量の汚れや細菌、化学物質が含まれる可能性があるのです。
そして、もうひとつの大きな変化――それが**「水道の民営化」**です。老朽化と財政難を背景に、全国の自治体で水道運営を民間に委ねる動きが進んでいます。果たしてそれは、私たちの生活にどんな影響をもたらすのでしょうか。

老朽化する水道管と、進む民営化の波
かつて日本の水道は、「世界でもっとも安全」と言われていました。しかし、今やその安全神話が少しずつ崩れ始めています。
水道事業は本来、各自治体が管理する「公営事業」。ですが、人口減少と節水意識の高まりで水道料金の収入が減少し、老朽管の交換費用をまかなうことが難しくなっています。ある調査では、全国の上水道事業者の99%が、老朽設備の更新資金を十分に確保できていないと指摘されています。
その穴を埋める手段の一つとして国が推進しているのが、「民営化」、つまり**官民連携(コンセッション方式)**です。2018年の水道法改正により、民間企業が自治体に代わって水道運営を担うことが可能になりました。
日本で初めて本格導入されたのは宮城県。2022年から、県内の上水道や工業用水の運営を20年間、民間企業コンソーシアムが受託する形でスタートしました。この制度では、水道施設の所有は県が持ちながらも、運営やメンテナンスは企業が行うという形。表向きには「効率化」や「コスト削減」を掲げていますが、実際には災害時の対応・水質管理・料金上昇への懸念が根強く残っています。
海外ではすでに多くの民営化事例がありますが、その中には失敗も少なくありません。たとえば南米のボリビア・コチャバンバでは、民営化後に水道料金が一気に跳ね上がり、市民の抗議運動が暴動に発展。結局、再び公営に戻る結果となりました。一方、イギリスでは1989年に水道を民営化しましたが、料金は30年で約1.5倍に。確かに設備投資は進みましたが、生活者の負担は増えたという現実があります。
民営化の本質は「誰が責任を持つか」という問題です。これまで自治体が担ってきた“公共の使命”が、利益を追求する企業の手に移る――。そのとき、私たちの水は本当に守られるのでしょうか。

最悪の未来と、現実的な変化
もし、このまま老朽化と民営化が同時に進行したら――。そこに待っているのは、次のような最悪のシナリオかもしれません。
蛇口から“赤水”が出る日常 老朽化した管から溶け出した鉄や鉛が混じり、飲み水として不安なレベルに。 お茶や料理にも影響が出て、「もう水道水は使えない」と感じる人が増えます。
水道料金の高騰 企業が利益を確保するために料金を値上げ。 現在、全国平均で月3,000円台の水道料金が、将来的に6,000円を超える可能性もあると試算されています。 家庭にとっては、見えない固定費の増加です。
断水・事故の増加 老朽管の破裂事故や漏水が増え、道路陥没や大規模断水が相次ぐ恐れがあります。 実際に、2025年春には神奈川県鎌倉市で約1万世帯が断水する事故が発生しました。 これは他人事ではありません。
しかし、現実的には“そこまで極端な事態”には至らない可能性もあります。水質基準は国が管理しているため、行政監督下で最低限の安全は保たれるでしょう。ただし、見えないところで少しずつ変化が進みます。
水道料金が数%ずつ上昇
「赤水」や「水圧低下」が地域的に発生
災害時の復旧が遅れ、備えの格差が広がる
自治体と企業の責任範囲が曖昧になり、トラブル時の対応が遅れる
これらは、実際に今もじわじわ進行しています。つまり――“静かな危機”なのです。

自分たちの水を守るためにできること
ここで大切なのは、「不安を抱えること」ではなく、「備えること」です。行政や企業の動きを待つだけでは、私たちの生活を守ることはできません。家庭単位で“水を守る力”を持つことが、これからの時代には欠かせません。
1. 家庭用浄水器・UFB機器を活用する
もっとも手軽で効果的な対策が、家庭での最終浄化です。蛇口直結型や据え置き型の浄水器は、残留塩素・微細な錆・雑菌を除去します。さらに近年注目されているUFB(ウルトラファインバブル)技術は、水中にナノサイズの気泡を発生させることで、配管内部のスケール(汚れ)付着を抑え、水そのものを活性化させる仕組み。
つまり――「水をきれいにする」だけでなく、「配管を守る」ことにもつながります。これは、まさに“家庭レベルの水道維持”とも言える取り組みです。
2. 宅内配管の点検・更新
築年数の経った戸建てでは、自宅の配管そのものが劣化していることもあります。水道メーターより先の管は所有者の責任範囲。年に一度、業者に点検を依頼するだけでも、漏水や錆を早期に発見できます。特に1970〜90年代に建てられた住宅では、鉄管や鉛管がまだ使われているケースもあり、健康面から見ても交換を検討する価値があります。
3. 災害・断水への備え
水は「止まってから備える」のでは遅いもの。飲料水のペットボトル備蓄や、簡易タンク、携帯浄水器を常備しておくと安心です。最低でも**3日分(1人あたり9L)**を目安に確保しましょう。最近では、空気中から水を生成する家庭用装置なども登場しています。“水を作る時代”が、すぐそこまで来ているのかもしれません。
4. 地域で「水」を見守る
自治体の広報誌や検針票に目を通し、水道局が出す老朽管更新計画を知る。ご近所で節水活動や情報共有を行う――そんな地域のつながりも、長い目で見れば「自分たちの水」を守る力になります。
結び
私たちの生活は、水に始まり、水で終わります。その“当たり前”が失われたとき、初めて私たちは水の尊さに気づくのかもしれません。でも今なら、まだ間に合います。
蛇口の向こう側で起きている現実を知り、家庭の中から、できることをひとつずつ。
「水を守る」という選択は、未来を守ることでもあります。




