いつから“水を買う”ようになったのだろう?
- 西園寺ケン
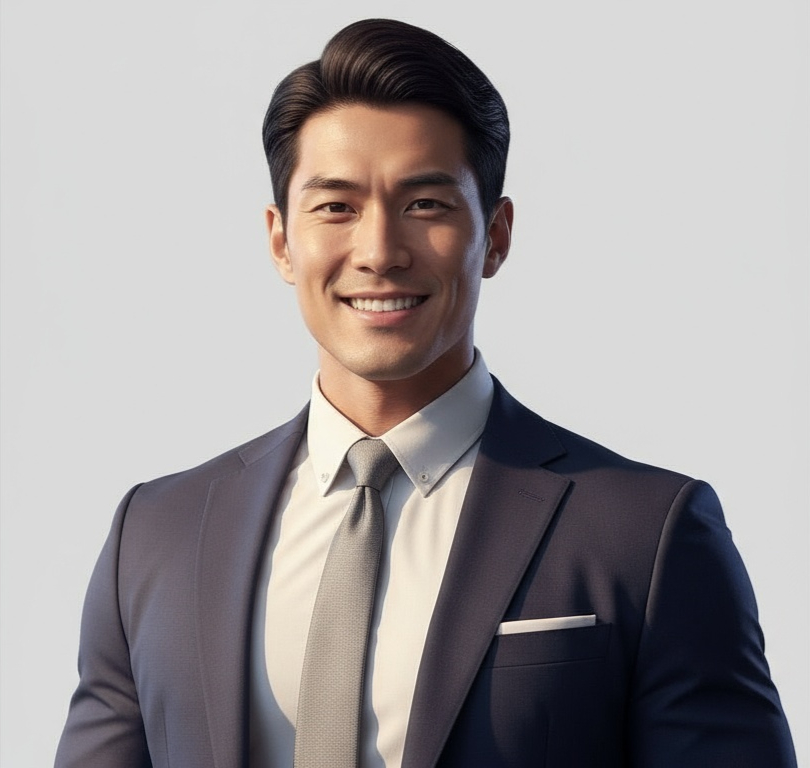
- 2025年11月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月15日
目次
気づけば冷蔵庫に“水のストック”
増え続けるボトルウォーターとその背景
“水道水離れ”という静かな変化
水を買うこと、それは安心を選ぶこと
気づけば冷蔵庫に“水のストック”
気づけば、家の冷蔵庫にペットボトルの水が数本並んでいる――。それはもう特別なことではなく、今の暮らしでは自然な光景です。子どもの部活やお出かけ用、料理やお茶を淹れるとき、寝る前の一杯。いつでもどこでも「安心して飲める水」がそばにあることが、私たちの日常を支えています。
昔は“蛇口の水”が当たり前でした。けれど今は、“選ぶ水”が当たり前になった。この小さな変化の中に、暮らしの価値観の移り変わりが見えてきます。

増え続けるボトルウォーターとその背景
日本のボトルウォーター市場は、この20年でおよそ3.5倍に拡大。2024年には5,000億円に迫る規模となり、飲料市場の中でも存在感を増しています。
その背景には、「安心・安全」への意識の高まりがあります。「ただ飲める水」ではなく、「気持ちよく、信頼して飲める水」を求める人が増えました。塩素のにおい、配管の老朽化、貯水タンクの衛生状態――。安全だとわかっていても、少しでも不安を感じたときに、人は“より確かな選択”をしたくなるものです。
そしてもう一つは、防災への備え。災害が多い日本では、非常時に備える意識が年々高まり、「水を買ってストックする」ことが安心の象徴となりました。実際、家庭の約7割がペットボトル水を常備しているとも言われます。それは“いつもの生活”と“もしもの時”をつなぐ、安心のラインです。

“水道水離れ”という静かな変化
内閣府の調査では、「水道水をそのまま飲む」と答えた人は43.9%。裏を返せば、6割近くが浄水器や市販の水を利用しています。
これは“安全基準”の話ではなく、“感覚”の変化です。味、におい、見た目、そして安心感。暮らしの中で大切にしたいのは、数字では測れない“気持ちの部分”です。
たとえば、「子どもにはできるだけいい水を飲ませたい」。そんな思いから、浄水器を設置したりボトルの水を選ぶ家庭が増えています。水を変えることで料理の味やお茶の香りが変わる――そんな実感が、“水を選ぶ時代”を支えているのかもしれません。

水を買うこと、それは安心を選ぶこと
水を買うことは、ぜいたくではなく“安心を選ぶ行動”です。冷蔵庫の中の一本のボトル、シンク下にあるカートリッジ――それらは「大切な人に安心を届けたい」という思いの形でもあります。
この行動は、誰もが持っている“やさしさ”の延長線上にあるのかもしれません。「これなら大丈夫」と思えるものを選ぶこと。それは、暮らしを少しでも気持ちよくするための知恵であり、愛情でもあります。
水道からの一滴、ボトルからの一口、浄水器からの一杯。どんな形であっても、水は私たちの暮らしを支える命の源です。そしてその中に、“選ぶ”という意識が加わった今、水は単なる飲み物ではなく、「信頼」の象徴になりました。

結び
“水を買う時代”とは、私たちが安心を大切にするようになった時代でもあります。それは、自然から離れたのではなく、より丁寧に暮らしを見つめ直す選択。
水を買うという行為の中には、家族を思う気持ちや、健康を守りたいという願いが息づいています。日常の中で、私たちは今日も静かに――「安心」を選びながら生きているのかもしれません。



